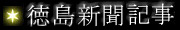
「老いと若の出会いを求めて」 
(徳島新聞2004年1月26日付け朝刊) 「年をとるのは素敵なことです/そうじゃないですか」と歌いかけたのは中島みゆきであった。この「傾斜」(『寒水魚』)というタイトルの歌を聴いた時、年をとることを力強く肯定する思想と感性が必要だと強く思ったものである。 この25年来、わたしは老と幼ないし若の再結合の必要性を訴えてきた。『翁童論』4部作(新曜社)はその過程でできあがった本である。近作の『神道のスピリチュアリティ』(作品社)の中でも、「翁童存在と現代文化の危機」と題して老いと若の問題を論じた。子どもと老人がふたたび深く出会い、結びつかなければならないと。 わたしの観点は、「老人の中には子どもがいる。同様に、子どもの中には老人がいる」というものである。この話を学生にすると、納得したような、しないような、不思議な顔をする。「老人の中に子どもが棲んでいる」という見方には大半の学生が肯く。自分自身の祖父母や身の回りの老人を見ていてそう実感したことが経験的にあるからだ。 だが、「子どもの中に老人が棲んでいる」と言うと、みんな、「そんな馬鹿な!」と怪訝な顔をする。そこからはっきりと、「子どもは子どもだ。何で老人であるものか。子どもと老人は対極にあるもの」という主張が読み取れる。 常識的に考えればそのとおりであろう。子どもの中に老人を見てとることは、外見からだけ判断すると不可能である。しかしここに二つの補助線を引いて見るとどうなるか。 一つは、柳田國男が『先祖の話』で展開した生まれ変わりや輪廻転生の思想である。柳田は、日本人は祖父母や曽祖父母が孫となって生まれ変わってくると信じていたと主張する。とすれば、このような見方からすれば、子どもすなわち孫は、祖父母の新生した姿である。 「この子はおじいちゃんに似ている」とか「曽ばあちゃんに似ている」と言って、連続性や類似性を見い出すところに、DNAという生物学的共通項と、もう一つ、魂の同一性という共通項を直観していたのである。日本人は古来、「血」の中にもう一つの「チ=霊」を見ていた。「ちはやぶる神」の「ち」もそうしたもうひとつの「チ=霊」のことである。 そうした考えを表す沖縄の方言に「ファーカンダ」という言葉がある。これは孫と祖父母をセットで呼ぶ呼び方で、「ファー=葉」と「カンダ=蔓」の合成語であるという。孫と祖父母が蔓と葉っぱのような関係であるとすれば、それは相互に一つながりの中の別の現われだといえるだろう。 とすれば、「子どもの中に老人がいる、孫の中に祖父母がいる」と言ってもおかしくはないだろう。実際、このような見方は、沖縄だけでなく、日本列島全体にも、またネイティブ・アメリカンやアフリカやオーストラリアの先住民の人間観にも共通する見方である。これはより古層にある人間観なのだ。 もう一つの補助線は、輪廻転生思想や霊魂観に基づいて、「知ることは思い出すことだ」と主張したプラトンの考え方である。知ることが「思い出すこと」であるとするならば、わたしたちはすでにさまざまなことを知っている。だが、なにゆえにか、そのことを忘れている。物忘れの激しい老人のように。しかし思い出せば必ずその記憶は蘇ってくる。「哲学とは思い出す術である」というのがプラトン哲学の要諦であった。 けれども、今日、このような考え方は「死期」となってしまっているように見える。わたしの「翁童論」4部作や『神道のスピリチュアリティ』は、そのような「死語=死児」となってしまった思想にあえてもう一度神話と哲学の息吹を通わせ「詩語」として蘇らせようとする反時代的な試みである。 要するに、有用でなくなった人間を「粗大ゴミ」とか「産業廃棄物」として排除し蔑むような人間観を打ち破っていきたいのだ。そしてどのような人間やいのちにも、ある不変で平等な存在の刻印と尊厳があるという、存在の意味と価値を再発見したいのだ。 少子高齢化社会を豊かに深く生きぬくためには、もう一度自分自身の存在の淵源を見つめ直す必要があるのではないかとわたしはいつも思う。 確かに、例えば、老人介護の問題は口で言うほど容易くはない。そのため、介護疲れでキレタり、爆発したりして老人虐待に走ったり、またその反対に幼児虐待に陥ったりする人が少なくない。人が人の世話をするということは容易いことではない。大変なことだ。それは承知している。わたしの家族もそうだから。 しかし、そこにもう一つの観点を入れてみよう。ソクラテスやプラトンが強調した、「人が生きていく上でもっとも大切なことは『魂の世話』をすることだ」という観点を。老人を介護し、子どもを育てるいとなみの中に、「魂の世話」をし、「スピリチュアル・ケア」をするという観点を受肉する時、人生にまったく新たな価値と光明と展望が啓けてくるのではないだろうか。 つまるところ、子どもの老人もみな永遠からの贈り物なのだから。 |