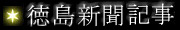
共同通信配信:オウム麻原判決対談 「最終解脱者の犯罪 日本人の心の針路を問う」 ◎山折哲雄(国際日本文化研究センター所長・仏教学) 〇鎌田東二(京都造形芸術大学教授・宗教哲学・神道学) *司会・ 松田博公(共同通信編集委員) 北海道、デーリー東北(青森・八戸周辺)、山形、上毛(群馬)、山梨日々、静岡、岐阜、徳島、愛媛、四国(香川)、高知、山陽(岡山)、山陰中央(島根)、日本海(鳥取)、西日本、佐賀、熊本日々、南日本(鹿児島)、琉球新報、沖縄タイムス (2004年2月27〜29日に各紙掲載) ▽ 悪魔的な人物 ―― 事件の衝撃から。 山折: 麻原彰晃とは地下鉄サリン事件の数年前に雑誌の対談で会っています。とうとうと仏教について話す。かなり正確な知識でした。しかし、既に太っていて、体はがたがたという感じ。空中浮揚をするというのもフィクションかと思いました。わたしが、教祖たるものはしっかりした体をつくらなくては、と率直に言うと、ニヤッと笑ったまま答えない。 彼が教団のサティアンの隠し部屋で捕らえられたときには、直感的にドストエフスキーの「悪霊」の主人公、得体の知れない巨悪をなし、人間の根源的なニヒリズムを体現する悪魔的な人物のことを連想しましたね。 鎌田: 地下鉄サリン事件の起きた1995年3月20日は、わたしの誕生日だったこともあって、事件の印象は痛烈でした。まず、非常に深い悔いがわきました。それ以前から麻原彰晃の教義の問題点、危険性を予感し、多少の批判的な文章を書いていましたが、もっと明確に指摘しておくべきだったと。この事件は宗教研究者としての自分にも何らかの責任はある。責任をどう果たせばいいかと悩みました。 ▽ 宗教の負の側面 ―― オウム教団を生んだ社会的背景について。 山折: 麻原の犯罪が発覚してから現在まで続くいらだちが、わたしにはあります。事件後やって来た取材記者や編集者は、例外なく「宗教には無関心」と言った。メディアに代表される社会の宗教への無関心、無宗教の態度が、オウム真理教問題に鈍感な対応をとらせてきたと思います。 もう一つ、事件後、宗教界も学界も「オウムは宗教じゃない、仏教じゃない」と排除した。これにも驚きました。麻原は権力欲、金銭欲を持っていた。人間誰もが持っている欲望を、より強烈に発酵させ、反社会的なテロリズムに導くものとして宗教が酵母の役割をした。問題はそこです。 宗教には人々を救済すると同時にそういう負の側面が本来ある。いい宗教と悪い宗教があると言っている場合じゃない。宗教が暴力と結びついた歴史的な先例は、欧州のキリスト教十字軍やわが国の一向一揆など幾つもある。宗教の専門家たちがそれにフタをし、宗教は平和で安全で癒やしを与えるもので、オウムは宗教と関係ないと言っている限り、事件の本質は見えてこないでしょう。 鎌田: 若者がオウムにひかれた理由の一つは、オウムほど明確にイニシエーション(通過儀礼)の重要さを主張した教団はなかったからだと思います。現代社会では、子どもが大人になる途上の人格のモデル、成長、向上の理想型が崩壊している。そこに、最終解脱者というモデルを提示し、出家して修行すればこうなれるんだというふうに、身体テクニックを疑似科学的に説明してみせた。 そして説法で、人生の目的とは、生の意味、死の意味とは何かをテーマに語った。こういう言説は、大学にも家庭にも地域社会にも既成の教団にも、ほとんどなかったのです。「自分探し」という若者の潜在的な欲望に、麻原は一つの回答を与えた。それは間違った回答だったわけですが。 山折: 人類は数千年の歴史の中で、通過儀礼という形で人間の成長のプロセスをシステム化してきた。それは親と子、師と弟子という垂直の関係を軸にしていた。この垂直の関係と友達や仲間の水平の関係が交差して文化が生まれ、新しい世代に継承されていく。技術、学問、芸術、宗教、政治、すべてそうだった。 そのイニシエーションの構造を自らぶちこわした現代社会が、それを求める若者を作りだした。若者は垂直の声として「おれこそグルだ、最終解脱者だ」と語る偽カリスマに、コロッと参ってしまった。社会にも重大な責任があります。 ▽ グルの絶対神格化 ―― 麻原被告と弟子が過激化する構造は? 鎌田: 麻原は最終解脱者である自分の人格、データをすべての弟子がコピーせよ、グルのクローンになれ、ヘッドギアをつけろ、血を飲め、DNAを摂取せよと、さまざまなイニシエーションを仕掛けた。わたしはとても危険だと思ったが、そうしてグルの絶対神格化をたどったオウム教団は、閉鎖的になり、内部での殺人や坂本弁護士一家の殺害、二つのサリン事件を起こしていく。その過程で、「ポア」の殺人教義も打ち出される。 山折: 麻原は目的を達成するため弟子に、「マハームドラー」(修行のための試練)を操作的に使いました。これはオウム事件を理解するのにカギとなる、非常に重要な概念です。 麻原が指令をする。「ポア」という言葉で暗示したかもしれない。弟子はそれがやりたくない困難な課題であればあるだけ、これも修行の試練だと自分を納得させる。これは、考え方によっては、師と弟子の究極の絶対的な関係の姿です。 鎌田: 麻原の密教的ワールドが怖いのは、彼が弟子の精神世界にどこまでも入り込んでくるからです。どこまでも修行。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。お前が今与えられている困難な事態は修行だ。獄中に入っても修行、死んだ後も修行。この修行依存症のアリ地獄に落ち込んだら、殺人は修行ではないと見切って脱出するのは難しい。 ▽ 師匠を見極める ―― このような宗教テロの再発は防げるか。 山折: 日本では、シャカとアーナンダ、達磨と慧可、法然と親鸞といった師と弟子の関係、もっと抽象化して言えば世代間の文化継承のあり方を、きちんと教育してこなかった。あらゆる宗教が弟子は師を越えていかなければならないと説いている。その観点があれば、オウム事件の危険は避けられたかもしれない。 鎌田: 麻原は最終解脱者を名乗った。その最終解脱の内実を問う力があまりにも弱かった。シャカもイエスも修行の過程で悪魔やサタンの誘惑を乗り越えています。魔や魔境、欲望といったものに今まで宗教的指導者がどう対決してきたのか。それを踏まえて、師匠は一体なぜ師匠なのか、精神的なレベルの内実はどうなのか、きちんと点検し、見極めなくては。 山折: この数十年の日本における癒やしブームは、大きな否定的意味を持っていると思います。オウム信者も癒やしを求める受動的な人間ばっかりだったような気がする。癒やしブームは宗教的、政治的、経済的指導者を点検できない、主体的に生きる意欲を欠如した群衆を生み出した。それはいまだに続いている。このままでは、第二、第三の麻原はいくらでも出てくるでしょう。 鎌田: 麻原と弟子の犯罪は、業やカルマによるとしか言いようがない局面があるかもしれない。しかし、厳然として責任はある。 山折: 法の下の責任は取らなければならない。死刑であっても。しかし、それで一件落着とはいかない。 鎌田: 最終解脱者を名乗った人にも、殉じた弟子にも生涯償い続けなければならない宗教的、普遍的な責任があります。法で裁けば済む問題ではない。 |