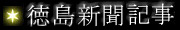
「ローマ法王選出に思う」 (徳島新聞2005年 5月25日掲載記事) 4月19日、新ローマ法王にドイツ人のラツィンガー首席枢機卿が選ばれた。カトリック教会内の最も強硬な保守派の一人とみられている。かつて、"他の宗教は宗教としてカトリックほど完璧ではない"と発言したことがある。 ラツィンガー枢機卿は、1927年にドイツ南部のバイエルン州に生まれ、13歳で神学校に入学。戦争中はナチスの青年組織に強制加入させられたこともある。前法王ヨハネ・パウロ二世が東欧ポーランド出身で、隣国ナチスドイツやソ連の圧制下で粘り強く宗教活動を展開してきたのとは対照的だ。 ラツィンガー枢機卿がヒトラー・ユーゲントの一員であったことに対して、ユダヤ教のラビ(宗教指導者)、メイル・ラオ師は問題視しないと冷静な対応をした。 新法王はこれまで、相対主義の時代風潮の中で絶対的な道徳価値を守ることを呼びかけ、カトリック至上主義を主張してきた。1981年以降、24年間もの長きにわたりバチカン教理省長官を務め、避妊や妊娠中絶、クローン胚研究、女性司祭登用に反対し、中南米で広がったマルクス主義系の「解放の神学」を徹底批判した。 この教理省はかつて「異端審問所」と呼ばれ、魔女狩りなどの異端摘発を任務としてきた。20世紀になって「検邪聖省」と名を改め、1960年代以降に「教理省」を名乗るようになった。異端審問官出身の法王は三百年ぶり、ドイツ系法王は950年ぶりだという。 故ヨハネ・パウロ二世は保守派ではあったが、日本を含む約130ヵ国を訪問し、他宗教・他文明との対話を実践して、「空飛ぶ聖座(法王)」と呼ばれ、世界平和への構築に重要な働きをした。 実は2001年6月、サン・ピエトロ寺院広場のミサで、私たちはローマ法王に謁見した。イタリア中東部のアンドレア市の招待で、世界遺産カステル・デル・モンテの中で天河大弁財天社の神事と神楽が奏された折、私もその一行の一員として参加し、神事に先立って法王との謁見の儀があったのだ。 既にそのころ法王は歩行にも困難をきたしており、常に付き添いの介助が必要であったが、そのカリスマ的人気たるや、アイドルスターをしのぐほどだった。車に乗って聖座近くまで入ってきたときの信者の熱狂ぶりは、ロックコンサートに来たのかと思うほどで、どこからこの人気が湧(わ)いてくるのか驚いたものである。 しかし、ヨハネ・パウロ二世にどれほど人気があったとしても、ヨーロッパでは確実に教会離れが進行している。一方、アフリカや中南米ではカトリック人口は増え、今回の新法王選出時には、アフリカや中南米出身の新法王誕生が期待された。実は私も、そうした期待を抱いた一人である。 カトリックが文字通り、「普遍的」になるには、非欧州出身の法王が必要ではないかと思うのだ。そこにおいて、諸宗教間の対話も文明間の対話もいっそう鋭く深く、互いの領域に入っていくことができるのではないかと期待する。 カトリックの総本山サン・ピエトロ寺院を中核とする「バチカン市国」は、イタリアの首都ローマ市内にある独立国家であり、周囲四キロにも満たない世界最小の国である。住民はほとんど聖職者で人口約五百人。しかし、世界中に約十一億人の信者を擁する。その頂点をなすローマ法王(教皇)の権威と影響力は大きいものがある。宗教家として最大の力を持つ位置にある。 そのサン・ピエトロ寺院は、「聖ペテロ(岩)の教会」という意味を持つ。イエス・キリストに従った十二人の弟子の筆頭に位置するペテロは、磔刑となったイエスの弟子であることを隠して逃げたことを悔い、その後、献身的な布教活動を続けてローマの地で殉教した。そのペテロの墓の上に、サン・ピエトロ寺院は建っている。 「汝の敵を愛せよ」と福音を説いたイエスの弟子たちが、2000年を経て、どのような「敵」の愛し方ができるのか−。期待と不安をもって第265代ローマ法王・ベネディクト16世の活動を見つめている。 |