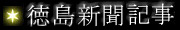
『宇宙戦争』VS『スター・ウォーズ3』 (徳島新聞2005年 7月23日掲載記事) 評判の映画『宇宙戦争』と『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』をその日のうちに続けて見た。映画館をはしごしたのは久しぶりだ。ほぼ同時期の封切りで、人気監督のスピルバーグとルーカスの一騎打ちという話題性もあったが、「9・11」以後の世界情勢の中で、この二人のエンターテインメントの大家が"宇宙の戦争"をどのように描いているか、大変興味があったのだ。 そして私なりに見比べてみて、軍配は『スター・ウォーズ』の方に上がると思った。 『宇宙戦争』は、著名なH・G・ウエルズの同名SF小説が原作だ。映画は息をもつかせぬスピーディーな展開を見せるが単調で、筋立ても戦争の動機もほとんど描かれることなく、ただただ破壊シーンの連続。「迫力があった! スリルがあった!」という感想に尽きてしまう。だがその「迫力」や「スリル」も心底すごいとは思えなかった。 1993年に製作されたスピルバーグの『シンドラーのリスト』には、戦争の破壊的暴力がリアルに描き出されていた。第二次大戦下ナチスドイツの侵攻したポーランドの古都クラクフで、ナチス党員の実業家オスカー・シンドラーは軍用ホーロー器工場を経営し、ゲットーのユダヤ人たちを雇い入れる。強制収容所に送られて情け容赦なく殺されていくユダヤ人を見て、彼は身の危険を冒して1200人のユダヤ人を救い出すことに成功する。収容所で殺された親族を持つスピルバーグはこの作品でアカデミー賞を受賞した。 私はこのとき、監督としてのスピルバーグの情熱と鎮魂の思いと戦争批判に感銘を受けた。だが、今回の『宇宙戦争』には、製作意図の違いがあるとはいえ、宇宙からの侵略者の理不尽な破壊がこれでもかとばかりに描かれていて、"なぜそこに破壊と戦争が生起するのか"という問いはなかった。侵略の恐怖と破壊のみ。 それに対して『スター・ウォーズ』もこれまたスピーディーな戦闘シーンが多く、途中でうんざりすることもあったが、主人公のアナキン・スカイウォーカーが、悪の帝国の使徒「ダースベイダー」に堕(お)ちていく過程がはっきりと描かれていて、興味深かっ た。誤解を恐れずに複雑な話の筋立てを捨象して言えば、それは「愛こそが悪への道である」という不条理のメッセージであった。 ルーカス監督は、アメリカの代表的な神話学者である故ジョセフ・キャンベルから多くを学んだ。『神の仮面』『千の顔を持つ英雄』『神話の力』などの著作で知られるキャンベルは、英雄神話の特徴を"旅と冒険と怪物退治"に見た。 その観点から見ると、悪に堕ちたアナキンは"怪物退治に失敗したアンチ・ヒーロー"であり、その子のルーク・スカイウォーカーは"怪物退治に成功したヒーロー"である。だが、そのような英雄と反英雄という二元対立が実は反転し、ねじれた入れ子構造になっているというのが、ルーカスの描くダース・ベイダー誕生の悲話である。悪は、愛と善意から始まったのだ。愛するものの喪失とその喪失への不安から。 アナキン・スカイウォーカーは奴隷だった。しかし子供ながら母を助け、天才的な能力を発揮して九歳で機械工学に開眼し、ロボットを作った。運動能力にも恵まれ、戦いに勝利を収めて奴隷の境遇から脱出するが、母親の自由を得ることまではできなかった。アナ キンは、平和の守護者「ジェダイの騎士」になる訓練を受けるために母に別れを告げ、旅立つ。そこには激動の冒険が待っていた。 アナキンはその修業と冒険の過程で「フォース(理力)」の行使を学ぶが、それを習得できずに終わる。<フォースにバランスをもたらす、選ばれし者>と期待されたにもかかわらず、道を踏み外すのである。それはいずれも「悪夢」を見ることから始まり、母の死に続いて、最愛の妻パドメを失うかもしれないという不安によって、抜きさしならぬ境遇に陥ってゆく。このアナキンの愛ゆえの悲劇的な悪への回路を、善なる回路へと修復するのがその子ルークである。 ルーカスが描くのは"善と悪""愛と憎しみ"という一見対立するかに見えるものが、実はあざなえる縄のごとくねじれ、相互浸入しているという事態だ。それは、アメリカが正義と善と民主主義の「騎士」であるという、ブッシュ大統領的な単純な言説を相対化するように見える。 少なくともルーカスは、戦いと悪の中に、すべての人間が抱くどうしようもない愛の力の介入を見ることによって、単純なものの見方や決めつけに静かな再考を促すのである。 |